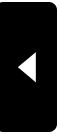2022年12月12日
 楽な路から六ツ石山
楽な路から六ツ石山
2022年12月11日 石尾根への楽な路はないものかと考えて、三ノ木戸から登った。 思ったほど楽ではなかった。






































Posted by tenkara1nen at 18:00│Comments(0)
│山歩き



 楽な路から六ツ石山
楽な路から六ツ石山