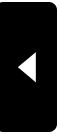2016年05月08日
 遠すぎる滝
遠すぎる滝
5月6日 妙見五段の滝を目指しても、私の足(釣り方、沢歩き)では辿り着かないのだ。

















とりあえず昨日は家の用事で一日中てんてこ舞いしながれも終了させて、今日は釣り券購入が必要な真木川へ行ってきました。 やっと真木川上流の状況が分かりました。 その話は後日。

















Posted by tenkara1nen at 20:00│Comments(0)
│小菅川



 遠すぎる滝
遠すぎる滝