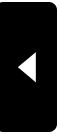2021年10月09日
 古礼山を目指し燕山で敗退!
古礼山を目指し燕山で敗退!
2021年10月8日 まだ行ったことのない古礼山に富士山と紅葉を求めた。 結果、疲れすぎて途中敗退する。


































































Posted by tenkara1nen at 20:50│Comments(0)
│山歩き



 古礼山を目指し燕山で敗退!
古礼山を目指し燕山で敗退!