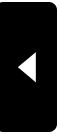2018年12月10日
 霧氷が寒い七ツ石山
霧氷が寒い七ツ石山
2018年12月8日 久しぶりに雲取山にあわよくば登ってみようとしたが、諸々の事情により七ツ石山で諦めてしまった。 山を舐めちゃぁいかん! 降参!



「ここまで1時間かかった人は雲取山頂まであと5時間かかります」 私の状況に近い、いや私のことを示す看板が見えた。 以前はなかったのに。














やっぱり、雲取山へ登る知力・体力がなくなったかもしれない。 次はあるか?



「ここまで1時間かかった人は雲取山頂まであと5時間かかります」 私の状況に近い、いや私のことを示す看板が見えた。 以前はなかったのに。














やっぱり、雲取山へ登る知力・体力がなくなったかもしれない。 次はあるか?
Posted by tenkara1nen at 21:45│Comments(0)
│山歩き



 霧氷が寒い七ツ石山
霧氷が寒い七ツ石山