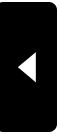2018年11月12日
 多摩川水系一の標高、唐松尾山
多摩川水系一の標高、唐松尾山
2018年11月10日 多摩川水系でもっとも標高の高い唐松尾山に登った。 朝のうちに登った西御殿岩は、とても素晴らしい展望に恵まれた。
























































Posted by tenkara1nen at 22:55│Comments(0)
│山歩き



 多摩川水系一の標高、唐松尾山
多摩川水系一の標高、唐松尾山