2012年11月05日
 雁ヶ腹摺山
雁ヶ腹摺山
11月3日 雁ヶ腹摺山に行ってきた。 登るつもりであったが、散歩程度になってしまった。

今日はあまり歩かなくても登れる雁ヶ腹摺山に決め、車を中央高速に乗せる。 しかし、運が悪い時はどこにいても運が悪い。 高速道路は、八王子インターから既にノロノロ運転である。 困ったものである。

大峠に到着すると、車の数に驚いた。 思わず数えると、ほとんどが道端に停めており、20台もあった。 なんと、車止めの路にテントを張っている御仁もいた。 ここは非常に有名な場所なのだと、情報不足を感じる。 それとも「山ブーム」のせいだろうか。

紅葉の終わったような林の中を歩き始めると、すぐに水場が現われる。 そこでは、石にタガネを打ち込む老人がいた。 御硯水と云うらしい。 大月市で唯一つの名のある水らしく、石板(名板)を立てる準備をしているという。 水を守る一助となればと云っていた。










今日はあまり歩かなくても登れる雁ヶ腹摺山に決め、車を中央高速に乗せる。 しかし、運が悪い時はどこにいても運が悪い。 高速道路は、八王子インターから既にノロノロ運転である。 困ったものである。

大峠に到着すると、車の数に驚いた。 思わず数えると、ほとんどが道端に停めており、20台もあった。 なんと、車止めの路にテントを張っている御仁もいた。 ここは非常に有名な場所なのだと、情報不足を感じる。 それとも「山ブーム」のせいだろうか。

紅葉の終わったような林の中を歩き始めると、すぐに水場が現われる。 そこでは、石にタガネを打ち込む老人がいた。 御硯水と云うらしい。 大月市で唯一つの名のある水らしく、石板(名板)を立てる準備をしているという。 水を守る一助となればと云っていた。









Posted by tenkara1nen at 21:00│Comments(0)
│山歩き



 雁ヶ腹摺山
雁ヶ腹摺山

























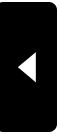

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。