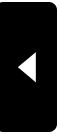2011年12月11日
 雪の雲取山
雪の雲取山
12月10日 雲取山に日帰りで挑戦した。



鴨沢の国道沿いの駐車場には車は1台しかない。 なるべく上から登るべく、林道を小袖川沿いに上り、少し上にある駐車スペースに車を停める。 国道沿いには車はなくても、ここには6台の車があり、二つのグループは登山の準備中である。 少し上った雲取山登山口には、さらに3台の車があった。 やはり人気の高い山なのである。 日本百名山、東京都最高峰、2,000m級! それにしても「寒い!」。

まずは林道から登山道に入り、林の中を登る。 時々朝日が差し込み、紅葉があったりもする。 そして鳥たちも、忙しそうに飛びまわり、綺麗な声を聞かせてくれる。 しかし昨日の雪なのか、登山道には結構積っており、場所によっては足を取られる。 登山一年生には難しい登山になりそうな雰囲気である。

単調な林の中の雪道を登り続け、堂所に着いたときには、すでに汗びっしょりであるのだが、それでも寒い。 暗い林の中から明るい尾根に出て、葉の落ちた広葉樹の広がる路を登る。 ふと振り返ってみると富士山が見えていた。 枝に邪魔されて、写真は難しいが、ずっと見えているので歩きに飽きない。 「あのカーブで見えるかも」と期待と失意の中で、私としては頑張って登っていくしかない。

真っ青な空が木々の間から覗き、日の光も差し込んで、気分の良い山歩きである。 登り続けて、汗びっしょりになって、最初の分岐にたどり着いた。 一息ついていると、ブナ坂へ向かう登山者に「いい杖ですね」なんて言われて、思わずにやつく。 しかし私を抜く人はみんな(6人)、ブナ坂に向かっている。 一瞬どうしたものかと考えたが、最初の予定通り小屋へ向かい、出発して2時間半、やっとのことで七ツ石小屋に着いた。


小屋から水場に登り、七ツ石山に向かって登る。 結構急な坂は、アイゼンは大袈裟のようだが、時々滑る。 やっぱり必要なのか。 一汗かいて縦走路に合流した。 これまでよりも雪が多く、木の枝に付いた雪(氷)が真っ白である。 最初は注意深く、道の塩梅を確かめながら歩く。 程なく荒れた七ツ石神社が現れたので、ご利益があるなしにかかわらず、お参りは欠かさない。



雪はあった方が滑らないが、踏み固められた雪道はよく滑る。 七ツ石山からの下りは滑ることなく進んだ。 尾根道はあまり起伏がなく、気持ちよく歩ける。 時々振り向き、左を見ると、いつも富士山が見えている。 その尾根の東京側斜面に奥多摩小屋が見えた。 小屋は、風雪から守られるように林の中にある。 小屋への道を一歩踏み込むと、鳥たちが一斉に飛び立った。 それもそのはず、自炊小屋などと書かれていて人の気配はしないし、母屋の横にある小屋は傾いている。 鳥の棲みかに変わっていたのだ。

比較的緩やかな道を、左に富士山を従えて、ゆっくりと進む。 途中二度の巻き道を、心を鬼にして真っ直ぐを選択し突き進む。 そんな偉そうなことではないが、二度とは来ない(来れない)かもしれないと思うと、巻くことはできなかった。 そんな歩きなので、小雲取山(1,937m)がどこだったかわからず、通り過ぎたようである。 山頂の避難小屋に続く最後の登りは、本当に、本当に最後の力を振り絞るように登った。 すでに5時間も歩いているのである。



下山中は登りの登山者に数多く擦れ違った。 この人たちは、ほとんど雲取山荘辺りに泊まるのであろう。 うらやましい限りである。 下山には、足腰のこともあり、巻き道を使う。 また、七ツ石山の縦走路は使わずにブナ坂を使って、ひたすら下りていく。 雪のあった日向の登山道はべちょべちょの道に変わり、林の中の登山道はカチカチのリンクに変わっている。 ところどころ足が滑るが、転ぶことはなかった。 なかなか優秀だと思った瞬間に転んでしまった。 私の詰めの甘さが露呈してしまった。




鴨沢の国道沿いの駐車場には車は1台しかない。 なるべく上から登るべく、林道を小袖川沿いに上り、少し上にある駐車スペースに車を停める。 国道沿いには車はなくても、ここには6台の車があり、二つのグループは登山の準備中である。 少し上った雲取山登山口には、さらに3台の車があった。 やはり人気の高い山なのである。 日本百名山、東京都最高峰、2,000m級! それにしても「寒い!」。

まずは林道から登山道に入り、林の中を登る。 時々朝日が差し込み、紅葉があったりもする。 そして鳥たちも、忙しそうに飛びまわり、綺麗な声を聞かせてくれる。 しかし昨日の雪なのか、登山道には結構積っており、場所によっては足を取られる。 登山一年生には難しい登山になりそうな雰囲気である。

単調な林の中の雪道を登り続け、堂所に着いたときには、すでに汗びっしょりであるのだが、それでも寒い。 暗い林の中から明るい尾根に出て、葉の落ちた広葉樹の広がる路を登る。 ふと振り返ってみると富士山が見えていた。 枝に邪魔されて、写真は難しいが、ずっと見えているので歩きに飽きない。 「あのカーブで見えるかも」と期待と失意の中で、私としては頑張って登っていくしかない。

真っ青な空が木々の間から覗き、日の光も差し込んで、気分の良い山歩きである。 登り続けて、汗びっしょりになって、最初の分岐にたどり着いた。 一息ついていると、ブナ坂へ向かう登山者に「いい杖ですね」なんて言われて、思わずにやつく。 しかし私を抜く人はみんな(6人)、ブナ坂に向かっている。 一瞬どうしたものかと考えたが、最初の予定通り小屋へ向かい、出発して2時間半、やっとのことで七ツ石小屋に着いた。


小屋から水場に登り、七ツ石山に向かって登る。 結構急な坂は、アイゼンは大袈裟のようだが、時々滑る。 やっぱり必要なのか。 一汗かいて縦走路に合流した。 これまでよりも雪が多く、木の枝に付いた雪(氷)が真っ白である。 最初は注意深く、道の塩梅を確かめながら歩く。 程なく荒れた七ツ石神社が現れたので、ご利益があるなしにかかわらず、お参りは欠かさない。



雪はあった方が滑らないが、踏み固められた雪道はよく滑る。 七ツ石山からの下りは滑ることなく進んだ。 尾根道はあまり起伏がなく、気持ちよく歩ける。 時々振り向き、左を見ると、いつも富士山が見えている。 その尾根の東京側斜面に奥多摩小屋が見えた。 小屋は、風雪から守られるように林の中にある。 小屋への道を一歩踏み込むと、鳥たちが一斉に飛び立った。 それもそのはず、自炊小屋などと書かれていて人の気配はしないし、母屋の横にある小屋は傾いている。 鳥の棲みかに変わっていたのだ。

比較的緩やかな道を、左に富士山を従えて、ゆっくりと進む。 途中二度の巻き道を、心を鬼にして真っ直ぐを選択し突き進む。 そんな偉そうなことではないが、二度とは来ない(来れない)かもしれないと思うと、巻くことはできなかった。 そんな歩きなので、小雲取山(1,937m)がどこだったかわからず、通り過ぎたようである。 山頂の避難小屋に続く最後の登りは、本当に、本当に最後の力を振り絞るように登った。 すでに5時間も歩いているのである。



下山中は登りの登山者に数多く擦れ違った。 この人たちは、ほとんど雲取山荘辺りに泊まるのであろう。 うらやましい限りである。 下山には、足腰のこともあり、巻き道を使う。 また、七ツ石山の縦走路は使わずにブナ坂を使って、ひたすら下りていく。 雪のあった日向の登山道はべちょべちょの道に変わり、林の中の登山道はカチカチのリンクに変わっている。 ところどころ足が滑るが、転ぶことはなかった。 なかなか優秀だと思った瞬間に転んでしまった。 私の詰めの甘さが露呈してしまった。

Posted by tenkara1nen at 22:50│Comments(0)
│山歩き



 雪の雲取山
雪の雲取山