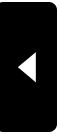2019年06月06日
 渓の杭をもう少し
渓の杭をもう少し
前回、工事だと記録した小さな木杭を改めて眺めてきた。 なかなか面白い。
◇赤道谷側
よく見る山奥の木杭、板杭でも日本語(名前)が書かれていることは珍しく、まるで街中の案内板のようだった。 案内板にしては、ちょっと小さいが。

◇ペンキとは?
山葵田が壊れたところの流れ、岩盤に木杭が石で留められていた。 流れにあるほかの杭とはちょっと違った。

<番号の枝番号>
「なんだよ~、番号がないのか~」
「すんません、間違ってしまって~」
「しょうがねぇの~」
「枝番付けましょうか?」
「やり直したくねぇからな~」
<ペンキ>
「真っ直ぐの線じゃなぁ」
「丸がいいんじゃないですか?」
「ん~任した!」
「このコンパスにペンキをつけて・・・」
丸が綺麗な円なのは、この理由がある。
◇泣かせる杭
このとき見た赤い頭の杭のなかには、尾根筋に打ってあるものもあった。 それが、なんとも泣かせる杭であった。

それよりも、この杭に書かれた数字が、なんとも泣かせる描き方になっているのが面白い。 最初「5」と書いたところ、前後の関係から間違いに気づき「7」と太い字で上書きした。 ところがこの「7」はすでに使っていたことを伝えられ、しょうがなく「6」と書いたのである。 もう上書きすることができないので、ぐちゃぐちゃにしたうえで、その下に書かざるを得なかったのだ。 なんとも泣かせる杭である。
◇赤道谷側
よく見る山奥の木杭、板杭でも日本語(名前)が書かれていることは珍しく、まるで街中の案内板のようだった。 案内板にしては、ちょっと小さいが。

◇ペンキとは?
山葵田が壊れたところの流れ、岩盤に木杭が石で留められていた。 流れにあるほかの杭とはちょっと違った。

<番号の枝番号>
「なんだよ~、番号がないのか~」
「すんません、間違ってしまって~」
「しょうがねぇの~」
「枝番付けましょうか?」
「やり直したくねぇからな~」
<ペンキ>
「真っ直ぐの線じゃなぁ」
「丸がいいんじゃないですか?」
「ん~任した!」
「このコンパスにペンキをつけて・・・」
丸が綺麗な円なのは、この理由がある。
◇泣かせる杭
このとき見た赤い頭の杭のなかには、尾根筋に打ってあるものもあった。 それが、なんとも泣かせる杭であった。

それよりも、この杭に書かれた数字が、なんとも泣かせる描き方になっているのが面白い。 最初「5」と書いたところ、前後の関係から間違いに気づき「7」と太い字で上書きした。 ところがこの「7」はすでに使っていたことを伝えられ、しょうがなく「6」と書いたのである。 もう上書きすることができないので、ぐちゃぐちゃにしたうえで、その下に書かざるを得なかったのだ。 なんとも泣かせる杭である。
Posted by tenkara1nen at 20:50│Comments(0)
│気になる写真



 渓の杭をもう少し
渓の杭をもう少し