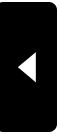2024年01月28日
 花のタグリスト
花のタグリスト
☂ 花など植物タグリスト その1
渓流釣りや山歩きで見た花が主である。 植物はとてつもない数があって、さっぱりわからないが、ほんの一部を調べてみた。 それでも正しい名前に辿り着いたのは極僅かである。 と云うことで、間違いだらけと云うこともあるので、助言いただければ幸いである。
知見も思うところも薄いので、ほとんどが受け売り状態だが、ちょっとだけ悪魔の辞典を意識してみた。

渓流釣りや山歩きで見た花が主である。 植物はとてつもない数があって、さっぱりわからないが、ほんの一部を調べてみた。 それでも正しい名前に辿り着いたのは極僅かである。 と云うことで、間違いだらけと云うこともあるので、助言いただければ幸いである。
知見も思うところも薄いので、ほとんどが受け売り状態だが、ちょっとだけ悪魔の辞典を意識してみた。

| 草 |
 羅生門葛(ラショウモンカズラ) 羅生門葛(ラショウモンカズラ)名前がいいね。 きっと昔から認識されていた花である。 昔のその人は、似ているものや色形ではなく、洒落た名前を付けたのだ。 しかし、どんな花も誰かに教えてもらわなければ、確かなことは分からない。 |
 山延胡索(ヤマエンゴサク) 山延胡索(ヤマエンゴサク)山以外は、何のことだかさっぱり分からない名前の小さな花である。 聞いたこともない言葉が続くと思えば、中国から来た生薬の名前だという。 分からない言葉でも仕方がないのだ。 |
 紫華鬘(ムラサキケマン) 紫華鬘(ムラサキケマン)色以外は何も分からない名前だ。 花はあっちこっちを向いていて、全く規則的に咲かない。 渓流にあって風に揺さぶられるからだろうか。 華鬘を調べて辿り着いても、見たこともないものなので、よく分からない。 |
 白藪華鬘(シロヤブケマン) 白藪華鬘(シロヤブケマン)そもそもムラサキケマンらしい。 花の根元が白くなれば紫が少なくなって白に見えるのだ。 そんなことが分かっても、私の同定能力が上がるわけではないのだ。 |
 山黄華鬘(ヤマキケマン) 山黄華鬘(ヤマキケマン)花があっちこっちを向いて咲き、その色が黄色いと何だか汚れて見えるから不思議だ。 特に問題なのは、ミヤマキケマンとの区別がつかない小ささと云うことである。 |
 深山黄華鬘(ミヤマキケマン) 深山黄華鬘(ミヤマキケマン)今まで見た花が正しい(不規則な方向を向く)形で咲いているのか分からない。 ヤマキケマンとの区別はつかないが、こっちの方が音の響きがいいので、ほとんどをここに分類している。 |
 関屋の秋丁字(セキヤノアキチョウジ) 関屋の秋丁字(セキヤノアキチョウジ)朝ドラ「らんまん」の主人公による命名という。 さすがにいい名前を付けますね~ これは何を意味しているのだろう、なぜこんな名前を、と思わず色々調べて納得してしまう。 |
 山苧環(ヤマオダマキ) 山苧環(ヤマオダマキ)最初見たときの驚きは今でも覚えている。 花だとは分かったが、どこから咲いているのか、一つの花なのか複数なのか、雄しべ雌しべはどこにあるのか、さっぱりわからなかった。 見た場所には今でも行くものの二度目は未だにない。 |
 黄花の山苧環(キバナノヤマオダマキ) 黄花の山苧環(キバナノヤマオダマキ)渓流脇の石のところにあって、これまた花がどうなっているのか分からなかった。 ヤマオダマキとはだいぶ違っているが、調べてみれば名前は「オダマキ」である。 花を探しに山へ行っているわけじゃないので、この花も一度しか見たことがない。 |
 東一華(アズマイチゲ) 東一華(アズマイチゲ)真っ白なので清楚に見える花である。 まさに春の妖精である。 何年も通う渓流で二度しか見たこと(記憶)がないのは何故だろうか? 妖精なので、きっと人目を避けて現れるのだ。 |
 九輪草(クリンソウ) 九輪草(クリンソウ)最初見たときには作り物かと思った。 個体別に色の濃淡があってなかなか楽しい花である。 渓流のすぐわきに咲いていることが多く、毎年見ることができる。 毎年見られるのは、毒があって鹿に食べられないことが理由なのだ。 |
 玉川杜鵑(タマガワホトトギス) 玉川杜鵑(タマガワホトトギス)最初に見たときは、これは花なのかと驚いた。 調べてみればホトトギスという名前が更に不思議に思えた。 気になったので調べれば、ホトトギス(野鳥)の胸の斑点に似ていて、黄色は京都のヤマブキの名所玉川からとって、タマガワホトトギスにしたという。 黒い斑点をホトトギスとしたのはなんとも楽しく、命名者の感性を羨む。 |
 山鍬形(ヤマクワガタ) 山鍬形(ヤマクワガタ)何が鍬形なのか、もしかしたらクワガタムシに似ているのか。 調べると、ガクの形が兜の鍬形に似てとあり、なんでガクの形を花の名前にしたのか、さらに兜の鍬形とは何か、気になることだらけである。 日本固有種らしい。 兜からカブトムシ、兜の鍬形から(赤脚)クワガタとなったのだ。 |
 人字草(ジンジソウ) 人字草(ジンジソウ)余り美しいとは思わなかった花である。 それは、花が枯れているように見え、白い花弁が二枚、垂れ下がっていたからである。 最近は山奥まで行かなくなって、全く見なくなってしまった花の一つである。 雪の下の種類はみな同じ形なので見分けは付かない。 |
 大文字草(ダイモンジソウ) 大文字草(ダイモンジソウ)雪の下の類は分からず、希望的観測の下、疑問符を付けたままダイモンジソウとしたものである。 |
 春雪の下(ハルユキノシタ) 春雪の下(ハルユキノシタ)雪の下の類は分からず、完璧に希望的観測の下、名前が気に入ってしまいタグをつけてしまったものである。 まぁ、いい加減にならざるを得ない知識である。 |
 仙人草(センニンソウ) 仙人草(センニンソウ)渓流の傍に咲くが、わりと民家が近いところで見る。 花ではなく種ができた姿をよく見る。 仙人の家近くに咲くからか、仙人が食べる雲に似た種を付けるからか。 花も種も靄がかかったように見えるからか? |
 竜胆(リンドウ) 竜胆(リンドウ)薬用にもなるといい、熊胆よりも苦いので竜胆というらしい。 私の見た(分類した)リンドウは図鑑とはちょっと違うような気もするが、ろくに調べもせずに、花の季節だけで決めたからだろう。 私の通った大学には龍潭というところがあったが、この龍潭は竜胆に由来しているのだろうか。 少~し気になった。 |
 春竜胆(ハルリンドウ) 春竜胆(ハルリンドウ)小さなリンドウで、周りにいろいろあったり、何もなくても日が当たらないと見逃してしまう小ささである。 背丈もなく本当に埋もれてしまう花である。 |
 筆竜胆(フデリンドウ) 筆竜胆(フデリンドウ)小さな花で明るい草地で見ることが多い。 更には花がたった一つだけで群生していないと云うこともあって、花に興味のない釣りの途中であれば見逃す確率が非常に高い。 発見するのはゆっくりしているときに限られる。 ハルリンドウとの迷いを、しっかり払拭するのは難しい。 |
 一人静(ヒトリシズカ) 一人静(ヒトリシズカ)試験管ブラシのような花は結構好きかもしれない。 渓流でははっきり見えて、何となくカメラを向けてしまう。 静御前が吉野山で舞った姿にたとえ吉野静とよばれ、二人静が出てきて、引っ張られるように一人静と名を変えたのだ。 あんまり似ていないと思うのだが名前だから仕方がない。 |
 二人静(フタリシズカ) 二人静(フタリシズカ)葉っぱが大きすぎてバランスが悪く、花は全く目立たない。 渓流ではとっても良く見るが、記録しようとはあまり思わない。 能の「二人静」における静御前とその亡霊の舞姿にたとえた。 きっとこれが大反響、大人気で、あやかろうとヒトリシズカに名前を変えたのである。 |
 姫蓮華(ヒメレンゲ) 姫蓮華(ヒメレンゲ)蓮華と云えばレンゲソウを想像するが、見た目には全くイメージが違う。 黄色い花が固まって、山になって咲く印象である。 渓流に流されて岩に留まっていた姿を見て、こんなところで咲くのかと勘違いした。 黄色い花では最も美しい花の一つである。 |
 岩煙草(イワタバコ) 岩煙草(イワタバコ)美しい形の花を見るのは難しいが、花は小さく紫色の星型で気に入りである。 葉っぱは煙草になるのかといつも考えてしまう。 葉っぱは大きめなので巻けば葉巻にはなりそうであるが、WWWを彷徨ってみても「吸える」とは、悪戯であっても見られなかった。 挑戦するしかないのか~ |
 山蛍袋(ヤマホタルブクロ) 山蛍袋(ヤマホタルブクロ)見られると嬉しくなってくる花である。 だいたい白と黄の花しかない山の中で、薄い赤の花は目につき、その姿が特徴的なのだ。 LEDライトを花に突っ込んで、本当のヤマホタルブクロを見なくてはいけない。 |
 蛍袋(ホタルブクロ) 蛍袋(ホタルブクロ)ガクに違いがあるというが、そんなところまで見ていないし写真に残すこともない。 しかし、いつもガクは見えないかと写真を穴が開くほど見るが、見えるのは後の祭りしかない。 標高が少し低いところなので、ホタルブクロである。 |
 山百合(ヤマユリ) 山百合(ヤマユリ)思わぬ場所で見る花で、白く大きな花にある色模様が、なんとなく毒がありそうに見えてしまう。 離れて見る分にはいいが、間近で見ると大き過ぎてそう感じてしまうのである。 |
 鬼百合(オニユリ) 鬼百合(オニユリ)赤いと云うか橙色のユリはやっぱり赤鬼なのだろう。 鬼と冠している通り、辺りと一線を画して人やほかの花を寄せ付けないのだ。 緑の中にポンと浮き出ているときが多い。 子孫はどうやって残すのだろうか? |
 小鬼百合(コオニユリ) 小鬼百合(コオニユリ)渓流の暗い岸辺にあって、何かの実が生っていると思うほど丸く見えた。 たった一本、独立して咲いており、その後幾度もその場所に通ったが見ることはなかった。 球根はどこかで生きているだろうか。 |
 走野老(ハシリドコロ) 走野老(ハシリドコロ)渓流では春先一番に葉っぱを見て、毒があるので鹿に食べられることなく、花が咲き終わるまでしっかり生き残る。 あまり綺麗ではないが、早春の渓流では外せない。 この花(葉っぱ)以外の緑はない、と云うところもあるほど繁栄している。 実際にはたくさん撮っているがブログにはあまり載せていない。 |
 山鳥兜(ヤマトリカブト) 山鳥兜(ヤマトリカブト)舞楽に使う冠(鳥兜)に似ているのはいいが、私には花には見えず豆のように見えてしまう。 だいたいが平たい渓流近くに並んでいることが多いので、人が育てていたのだと思ってしまう。 毒は薬草なのか? |
 奥鳥兜(オクトリカブト) 奥鳥兜(オクトリカブト)山と奧はどのように違うのだろうと考えてしまう。 ヤマトリカブトより奥(標高が高いところ)に生えているからか。 違いは全く分からない。 |
 山吹(ヤマブキ) 山吹(ヤマブキ)渓流釣りで岩魚が良く出始めるのが、このヤマブキが咲くころなのである。 そう云う理由でヤマブキには結構注意を払っている。 ただ、注意は払っても上手く写せるのと、岩魚がよく釣れるのとはちょっと違う。 ヤマブキは色にもなっているほど綺麗なのだ。 |
 吊舟草、釣船草(ツリフネソウ) 吊舟草、釣船草(ツリフネソウ)日本語で釣船草は気にらず、吊舟草のほうがいい、花の形に合っていると思う。 この赤紫の花は、どうしても綺麗だと感じられない。 理由は、しぼんで見えるからのような気がする。 花の形は特定の虫(虻)を頼りにしているらしいが、その虫を見たことはない。 |
 黄吊舟草、黄釣船草(キツリフネソウ) 黄吊舟草、黄釣船草(キツリフネソウ)ツリフネソウのように多くはないが、最近はよく見るようになった。 とっても綺麗だと思うのだが、何だかぼやけて見えるので、その綺麗さが半減してしまう。 黄色い花はボケて見えるのだ。 |
 猫の目草(ネコノメソウ) 猫の目草(ネコノメソウ)最初見たときは花だと思ったが、それが葉っぱだと知って驚いた。 路から流れに下りるところに小さな緑がたくさんあって、それがネコノメソウであった。 見たもの撮ってきたものを調べていくうちにたくさんの種類があることも知った植物である。 |
 汚れ猫の眼草(ヨゴレネコノメソウ) 汚れ猫の眼草(ヨゴレネコノメソウ)言われてみれば、葉っぱが他のネコノメソウよりも黒っぽいので、確かに汚れているように見える。 渓流釣りでは最もよく見るものの、失礼な名前を付けられた気の毒なネコノメである。 |
 蔓猫の目草(ツルネコノメソウ) 蔓猫の目草(ツルネコノメソウ)葉っぱの緑が黄緑色のものが多く、とても美しく見える。 蔓性なので他のネコノメより背丈があり目立ちそうだが、小さいので他の緑に埋もれてしまう。 |
 山猫の目草(ヤマネコノメソウ) 山猫の目草(ヤマネコノメソウ)猫じゃなくて山猫の目に見えることから名付けられた、と考えたい。 山猫は八重山諸島にしかいないと思っていたが、本州にもいたのだ。 この草の特徴を私は確認できず、山深いところで生きているからという理由で、希望として分類した。 |
 花猫の目(ハナネコノメ) 花猫の目(ハナネコノメ)苔だと思って一生懸命に調べたが分からなかったネコノメで、ブログの閲覧者から教えてもらって分かり、すっきりした花である。 小さくて白いので写真写りが悪く、はっきり写せたものは未だにない。 |
 叡山菫(エイザンスミレ) 叡山菫(エイザンスミレ)薄い桃色の花が控えめで、葉っぱの切れ込みが美しい。 私は菫の中で最も美しと感じる。 名前からして比叡山が関係していることが分かり、命名の頃の田舎学者に負けるかと京にゆかりの名前を付けたのである。 |
 立壺菫(タチツボスミレ) 立壺菫(タチツボスミレ)山で見る菫のほとんどがこれである(と思っている)。 いい形の花を見つけるのは至難の業で、気に入った花の形は稀である。 立坪菫とも書くようだが、立壺菫と書いた方が何となく日本らしく感じる。 色々漢字を宛てるのは音を大事にするからで、漢字は何でもよく、理由は後から考えるのだ。 |
 壺菫(ツボスミレ) 壺菫(ツボスミレ)背が高くなったり、地表を這ったりするらしい。 これはもしかすると坪庭に向いていたのかもしれないので、坪菫と書いていたかもしれない。 日本語は難しいのである。 |
 細葉立壺菫(ホソバタチツボスミレ) 細葉立壺菫(ホソバタチツボスミレ)全く覚えていない。 改めて確認すると細葉には見えないし、茎も伸びているのでツボスミレかもしれない。 今でも分からない。 |
 鬼田平子(オニタビラコ) 鬼田平子(オニタビラコ)マンションの坪庭で見る花である。 何が鬼なのかさっぱり分からないどころか、小さく可憐な花なのである。 こんな名前の花が庭にあるとは思わなかったことから、街中にもたくさんの知らない花があるのだと、改めて教えてくれた。 |
 片栗(カタクリ) 片栗(カタクリ)渓流釣りで使う路で咲くのを知っているし、近所の植物園でも咲く。 だいたいは片栗粉を作るために栽培している、していたか。 野山北公園では自生地を保護しているが、花の時期に行ったことはないので、どのくらいの数が咲くのかは知らない。 観に行った方がいいかな~ |
 狐の剃刀(キツネノカミソリ) 狐の剃刀(キツネノカミソリ)隣町の谷戸で見たもので、なかなか面白い名前だと思っている。 暗い中に炎(狐火)が見え、剃刀(葉っぱ)が立っている、なんてことのようだが、もう少し物語を聞きたい。 毒があって薬となるらしいが、「決して口にしてはいけない」との言葉から猛毒かもしれない。 |
 鷺草(サギソウ) 鷺草(サギソウ)鷺が飛んでいる姿に見える花が付く。 この花の形を見たいと思っていたら、昭和記念公園に情報があった。 実際見て感動した。 本当に鷺が羽を広げた格好の花である。 ただ、最もよく見る鷺ではなく、鶴とかにならなかったのか。 花の白さは鷺であるのだが。 |
 富士伶人草(フジレイジンソウ) 富士伶人草(フジレイジンソウ)全く覚えていないので確認して見ると、ヤマトリカブトのような感じであるが、当時は今より知識はなく、名前にも飢えていたのでそうしたに違いない。 若干、レイジンソウかもしれないとの気持ちはあるが、申し訳ない限りである。 |
| 木 |
 山桜(ヤマザクラ) 山桜(ヤマザクラ)山へ釣りに行くので数えきれないくらい見たが、近くで写せないことも多く、ブログにはほとんど載せていない。 我が街にも山桜の大木があるので、更に記録から外れてしまう。 |
 桜(サクラ) 桜(サクラ)桜には百を超える種類(名前)があって、死にそうな土手の染井吉野はなんとなく分かっても、その他は判別できない。 それでも何とか名前を探したものである。 ある時から、無駄な努力と諦めてしまった。 この桜の内、ある程度分かった桜 三春の滝桜 山高神代桜 染井吉野 河津桜 十月桜 枝垂れ桜 紅枝垂れ桜 |
 梅(ウメ) 梅(ウメ)桜と同様にとんでもない種類があり、桜との区別でさえつかない。 ずいぶん頑張って調べようとしたが、とても分かるものではなく、ある時から無駄な努力と諦めた。 この梅の内、分かる分類した 紅梅 白梅 蝋梅 素心蝋梅 |
 石楠花(シャクナゲ) 石楠花(シャクナゲ)花は大きく薄い赤が多い。 花びらの厚みはないが、葉っぱは分厚くて、形はまるでツツジである。 私が山歩きする袴腰辺りには非常に多く自生し、麓の一之瀬集落にも植えてある。 葉に痙攣毒があり、吐き気や下痢、呼吸困難を引き起こすというが、集落に多いと云うことは薬として使っていたに違いない。 |
 山躑躅(ヤマツツジ) 山躑躅(ヤマツツジ)赤から橙色に近い綺麗な花で、渓流釣りで脇で見かけるが、その数は少なく滅多にお目にかかれない。 ミツバツツジとの色の違いがいつも反対になるのは何故だろう。 |
 三葉躑躅(ミツバツツジ) 三葉躑躅(ミツバツツジ)紫色に近い花で、渓流釣りで使う林道を歩けば、季節にはだいたい見ることができる。 ミヤマツツジも同じような花なので、もしかしたら見ているかもしれない。 |
| その他 |
 蕗の薹(フキノトウ) 蕗の薹(フキノトウ)小菅村で見るとは思ってもみなかった。 半信半疑だったところ、閲覧者から教えてもらった。 ただ、成長し過ぎて食べられないようである。 しかし、それから二度と見ることがないのは、非常に残念である。 |
 洋種山牛蒡(ヨウシュヤマゴボウ) 洋種山牛蒡(ヨウシュヤマゴボウ)花の終りに見ただけで、ツマグロキチョウを撮ったというのが本当のところである。 |
Posted by tenkara1nen at 18:00│Comments(0)
│花のタグリスト



 花のタグリスト
花のタグリスト